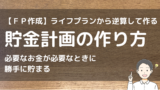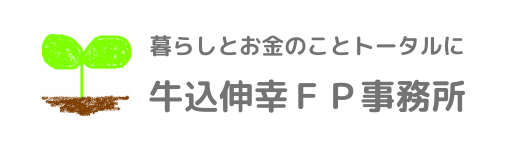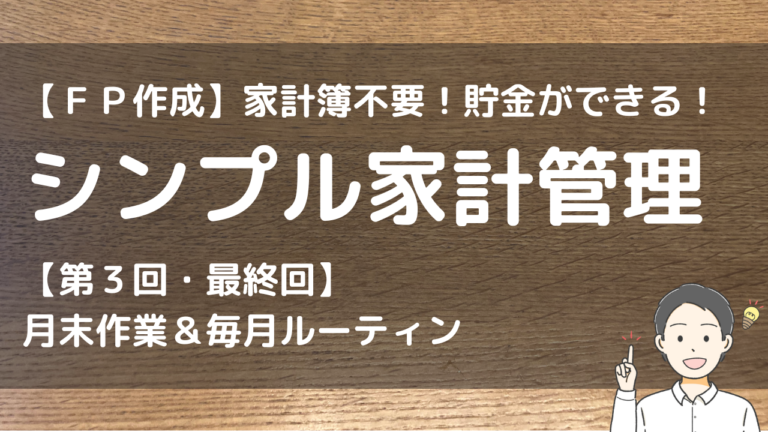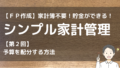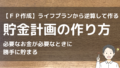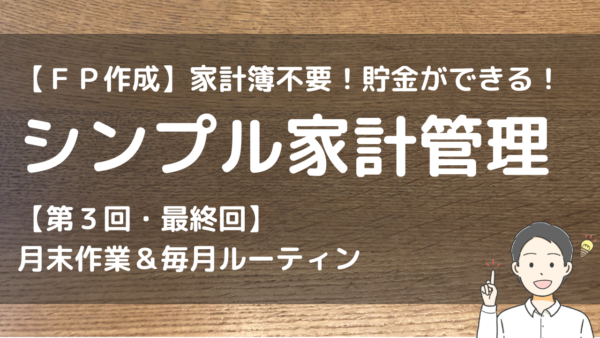
おはようございます。群馬県高崎市のファイナンシャル・プランナー(FP)牛込伸幸です。
今日も自分のできることを、たんたんとやっていきたいと思います^^
ここまでは、
・家計のお金を3つに分けて、
・それぞれの予算を決めてきました。
最初から読みたい方はこちら↓
https://fpushi.com/archives/336
今回は、復習も兼ねて「毎月どんな流れで家計を管理するか?」ご説明します。大きな流れは、
【ステップ2】日頃は目的別口座・お財布から支出
【ステップ3】月末に残高チェック
では、順にみていきましょう。
【ステップ1】月初に予算配分
毎月、決めた予算をそれぞれの銀行口座・お財布に配分します。「毎月同じ金額」を配分するのが家計管理のコツ。
例えば、こんな感じでした(くどいですが金額はひとつの例ですよ)↓
・貯金3万円
・毎月の生活費27万円(生活費口座15万円、家計の財布12万円)
・特別支出0万円
※実際の手取り収入が31万円だった場合、差額の1万円は「貯金」か「特別支出」に(つもり貯金ですね)
※この例では「特別支出」はボーナスで出す計画。毎月の収入からの配分はゼロに。
※塾や習い事の月謝などを現金で払う場合は封筒に入れるなどして別にしておく。家族のお小遣いはすぐに渡してしまう。
【ステップ2】日頃は目的別に使う
予算を配分したら、あとはそれぞれ目的別の銀行口座・お財布からお金を出します。
・住宅ローンや公共料金の引き落しは「生活費口座」
・テレビ(特別支出)を買ったら「特別支出口座」
・つみたてしていた貯金でクルマを買ったら「貯金口座」
とはいえ、日頃、意識するのは「家計の財布」だけでしたね。理由は、
・「生活費口座」は自動引き落し。予算配分をして、月末に引き落し状況をチェックするだけ
・「特別支出」は、そう多くない
【ステップ3】月末に残高を確認
月末にそれぞれの銀行口座・家計の財布(現金)の残高を確認します。
・「生活費口座」(口座引き落し)の残高が毎月少しずつ増えていれば、予算が適切な証拠(残高不足にならないように、10万円などキリのいい金額を予備で入れておく)
・「特別支出口座」の残高を確認して、あといくら使えるか?軽く確認。使うたびに内容と金額をメモしておくと、あとで振り返ることができる。また、今後の支出の予定をメモしておくのも効果的(例:6月エアコン20万円?)
・「貯金口座」の残高も一応確認
下のような表を作って残高を記録してもいいですね。

2月に前月比マイナスになっていますが、これは特別支出があったことが原因。
「毎月の生活費」(家計の財布・生活費口座)の残高は安定しているので問題ありません。
ちなみに、予算配分の作業は、月初(毎月1日)ぴったりにしなくても大丈夫です(大変ですよね)
・月末に残高を確認して、そのまま予算配分する
・または、お給料が出たら予算配分しておいて、月末に残高を確認する
どちらでもいいのすが、毎月同じ順番でやってください。
ただ、「家計の財布」(食費など現金支出担当)は、「月末」に残高を確認してから、翌月の予算(現金)を入れます(それまでは封筒などで保管)。予算内でやりくりすることを目指してやっているからです。
以下補足です。
※「家計のお財布」に全額入れるのはキケンなので封筒などと併用
※月末が休日で口座引き落しが翌月にズレた場合、引き落しが終わってから確認・記録する(毎月、同じ条件で残高を比べるため)
※「生活費口座」は1つが理想。学校の引き落しなど、銀行が指定されている場合は仕方ない。
※「貯金」用の口座は、定期預金、投資信託など複数あっても問題なし。
※締め日は「月末」でなく「給料日」などでもOK。自分がやりやすい日で。ただ、毎月同じに。
まとめと今後
以上「シンプルに家計を管理する方法」をお伝えしてきました。最後まで読んでくださってありがとうございました。
興味を持っていただいた方は、まずはこの方法で3か月ほどやってみてください。実践することで、適正な予算配分や、家計の見直しのポイントが自然と見えてくると思いますよ。
「家計の財布」(毎月の生活費の現金支出系)と「特別支出」については、今までのご説明だけでは大ざっぱすぎるので続編を準備しています。
食費はどう管理したらいいか?現金払いと電子決済をどう併用したらいいか?といった実践的な内容です。
それでは引き続きよろしくお願いいたします↓
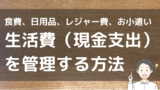
先に貯金計画をつくりたい方はこちら↓