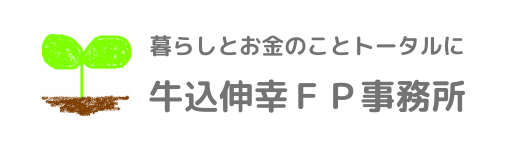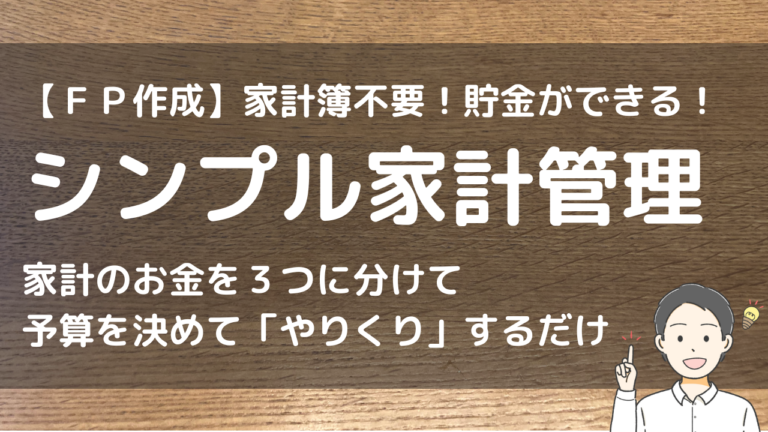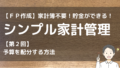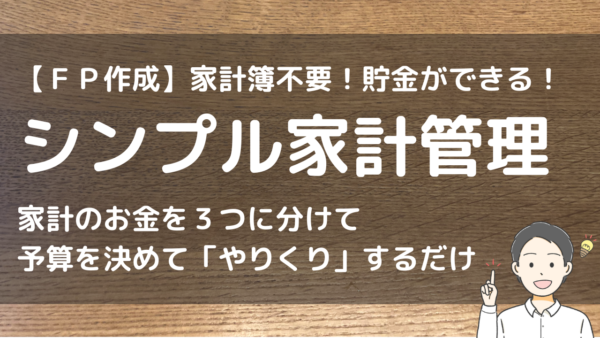
おはようございます。群馬県高崎市のファイナンシャル・プランナー(FP)牛込伸幸です。
今日も自分のできることを、たんたんとやっていきたいと思います^^
今回は、ぼくが実際に使っている、家計を管理する方法をお伝えします。あなたは、こんなお悩みはありませんか?
「ムダ使いしているつもりはないのに、なぜか貯金ができない」
「家計簿が苦手で長続きしない」
「家計簿はつけているのに、効果が感じられない」
「今のままで大学の教育費や老後資金は貯まるの?」
「つみたてNISAをしたいけど家計に余裕がない」
この記事は、あなたのこんなお悩みを解決したいと考えてつくりました。でも、何を隠そう、ぼく自身も家計の管理で悩んでいたのです。
仕事がら「無理のない住宅ローンの組み方」「必要最低限の保険の入り方」みたいな知識はありました。でも、浮いた分で貯金ができたわけではありません。
いろいろな家計簿を試したり、レシートを保存して月末に集計したりもしてみましたが、どれも長続きしませんでした。
そこで「できるだけ少ない作業で」「家計の必要最低限のことはしっかりと把握できる」方法を試行錯誤しながらつくってきました。
特に「日々の支出を記録しない」点にこだわりました。
これからお伝えする方法は、その後も細かな試行錯誤は続いていますが、今の形に落ち着いてから20年以上、実際に自分で使っています。
ぼくの事務所のお客さまやインターネットの講座でご紹介して、ご好評をいただいています。
基本的な方針はこうです。
・家計簿不要(日々の支出は記録しなくてOK)
・それでいて、家計の必要最低限のことはちゃんと把握できる
その結果、
・必要なときに必要なお金が貯まる(自信と安心感が生まれます)
こうなるためには、考え方(マインド)も大切です。
家計の「しくみ」だけでは限界があります。やっぱりここが整っていることが大事。
もちろん、気合いや根性、ガマンではなく、無理せず自然とできる考え方(マインド)です。
この方法は、家計簿をつけている方にも役立ちます。家計のしくみを整えたうえで、家計簿で支出を記録すれば最強ですね。
・・・
それではさっそく始めます。
お金のことをあまり気にしないで暮らせること(もちろん、ちゃんと管理してですよ)を目指して、一緒にがんばりましょう!
家計のお金は3つに分ける
できるだけシンプルな方法で家計を管理するといっても、ひとつの銀行口座でお金を管理すると、うまくいきません。
いろいろ試したのですが、家計のお金は3つに分けるとうまくいきます。では、順にお話していきます。
【ステップ1】貯金口座をつくる
ひとつの銀行口座にお金を入れておくと、
・今いくら貯まっているのか?
・今月はいくら使っていいのか?
これがハッキリしません。銀行口座の残高を見たときに、500万円入っていたとしても、
・来月、クルマを買い替える予定がある
・大学の教育費や老後資金のつみたて貯金も入っている
としたらどうでしょう?
使う予定のあるお金を差し引くと、実は「使っていいお金はあまりなかった」なんてことも。
逆に、口座を一緒にして「貯めるお金」と「使うお金」の境界線がないと、何となく使ってしまうものです。
いくら使っていいのか?わからなくて、安心してお金を使えないなんてこともあります。
ひとつの口座で管理して、内訳を計算して「今いくら貯まってる?」「あといくら使っていい?」を把握することはできます。
でも、計算しないとそれがわからない。このひと手間が「壁」になります。
ぼくも最初、できるだけシンプルにしようと思って、ひとつの銀行口座で管理しようとしました。でも、うまくいきませんでした(内訳を計算しないで放置…)
・・・
そこで、クルマや教育費、老後資金など貯めるお金(貯金)を専用の銀行口座を作って分けます。
口座を分けるのがポイントです。
すると、今いくら貯まっているか?今月はあといくら使っていいか?銀行口座の残高を見ればすぐにわかります。
お金を預けたとき、引き出したとき、自然と目に入ります。
こうすることで「使っていいお金」と「貯めるお金」に境界線ができます。
・使うお金(生活費口座)
・貯めるお金(貯金口座)
【ステップ2】特別支出口座をつくる
やっていくとわかるのですが、「貯めるお金」と「使うお金」の2つに分けるだけではうまくいきません。
毎月の予算を「使うお金」(生活費口座)に入れて、3か月ほど続けると、自分に合った毎月の予算が見えてきます。
「毎月○万円あれば暮らせるな」と、わかってきます。
ただ、何もない月はいいのですが、たまにある、ちょっと大きな支出(「特別支出」といいます)があると、すぐに毎月の予算をオーバーしてしまいます。
例えば、テレビなど家具家電の買い替え、子どもの部活道具、塾の夏期講習、自動車税、家族旅行、友人の結婚式など。こういった支出は結構あるものです。
毎月の生活費は一定でも、特別支出があると、毎月の支出のブレが大きくなります。これでは毎月の予算を決めても管理ができません。こんなイメージ↓

そんなとき「今月はテレビを買ったから、食費を切り詰めて…」なんてムリですよね。
結果、こうしたちょっと大きな支出のたびに、貯金を取り崩してしまう結果になります。
「子どもの教育費のつみたてを始めて貯まってきたのに、車検で仕方なく使ってしまった…」こんなことはよくあります。
そこで、こういった「たまにあるちょっと大きな支出(特別支出)」に対応するための予算をつくります。貯金と同じく、専用の銀行口座も作ります。それが特別支出口座です。
・毎月の生活費(生活費口座)
・特別支出(特別支出口座)
これで、家計のお金は3つに分けるの完成です↓
・貯金(貯金口座)
・毎月の生活費(生活費口座)
・特別支出(特別支出口座)
特別支出はわかりやすい基準がないと、これは生活費?特別支出?となってしまいます。そこで、「特別支出」の定義は「毎月は使わない、5,000円以上の支出」としています(詳しくは後ほど)
こうすることで、
・「毎月の生活費」は毎月の予算を決めて、そのなかでやりくりできる
・ちょっと大きな支出があっても「貯金」は目的以外では取り崩さない
こんな感じでお金の流れを整えることができます。
生活費と特別支出の違い
最初は「これって特別支出?毎月の生活費?」と迷うことがあるかもしれません。そこで具体例をあげてみます。
特別支出の定義は「毎月は使わない、5,000円以上の支出」でした。
例えば、住宅ローンの返済が毎月8万円の場合。金額は5,000円を超えていますが、毎月あるので「特別支出」ではなく「毎月の生活費」です。
1,000円のマグカップを買った場合はどうでしょう?
マグカップは毎月は買いませんよね。でも、これをいちいち「特別支出」にすると管理が大変です。ですから、5,000円未満は「毎月の生活費」です。
テレビを買った。これはドンピシャで「特別支出」です。毎月は買わないし、金額も大きいので。
衣類をまとめ買いしたら5,000円以上だった。これは「特別支出」でいいでしょう。ひとつひとつは5,000円未満でも、トータルで考えます。
5,000円?1万円?特別支出の基準
5,000円という基準もいろいろ試してみてください。
基準となる金額が低すぎると「特別支出」の件数が多くなって管理が大変になります。
逆に、基準となる金額が高すぎると、何でも「毎月の生活費」になって、予算内でやりくりすることが難しくなります。
最初は5,000円か1万円で試して、あう方を採用すればいいでしょう。
どちらがいいということはありません。やりながら自分にあう金額を見つけていってください。
特別支出の基準を5,000円以上にすれば、「毎月の生活費」の予算は少なくなり「特別支出」の予算は大きくなります。
逆に、1万円以上にすれば、「毎月の生活費」の予算は大きくなり「特別支出」の予算は少なくなります。
ただ、年間で考えれば同じですね(予算配分の方法は今後ご説明しますね)
・・・
最初は「これって特別支出かな?毎月の生活費かな?」迷うこともあると思います。
でも、慣れてくると、自分なりの基準ができてきます。とにかく統一的な基準で運用できればOKです。
あまり難しく考えすぎずに、まずは実践してみてください。
特別支出は年間100万円以上!?
ぼくが特別支出という予算をつくって感じたのは「ちょっと大きな支出は、ちょくちょくある」ということです。
季節ごとに衣類を買ったり、進学・進級シーズンには学用品や体育着、部活道具、夏休みになれば家族旅行や帰省、塾の夏期講習などなど。
また、ぼくの住む群馬県は持ち家、クルマ2台保有のケースがよくあります。固定資産税、火災保険、自動車税、自動車保険、車検、タイヤの買い替えなどがあります。
よくある例をあげてみました。どれもありそうなものばかりでは?↓
固定資産税(自宅)年間10万円
火災保険(自宅)7万円
自動車税(1台目)4万円
自動車保険(1台目)5万円
自動車税(2台目:軽自動車)2万円
自動車保険(2台目)4万円
車検(1台目のみとして)10万円
タイヤ(1台目のみとして)5万円
家族旅行10万円
ディズニー7万円
帰省(夏)3万円
帰省(年末年始)5万円
交際費・冠婚葬祭5万円
衣類まとめ買い(夏)3万円
衣類まとめ買い(冬)5万円
子どもの部活道具 1万円
夏期講習、冬期講習、春期講習 10万円?
テレビ10万円
エアコン20万円
【合計】126万円
これで年間合計126万円です。特別支出に年間100万円以上も!と驚くと思います。
実際、ぼくが自分で記録をつけたり、お客さまにやっていただいたりすると、100万円以上になっているケースが多いです。
思うように貯金ができないワケ
繰り返しになりますが、特別支出的な支出を「今月は余裕があるから生活費から出しておこう」「今回は仕方ない、貯金を取り崩そう」と、その場その場で対応していると、気がつけば貯金が増えていない、そんな状況に陥ります。
実は、ぼくも同じ悩みを持っていました。
貯まってきたと思ったら取り崩す…これでは「本当はいくら貯まっているの?」「教育費の貯金はできるのか?」わからなくなります。
原因は、このような「ちょっとした大きな支出は、ちょくちょくある」という認識がなかったこと。
つまり、予算が確保されていないことです。
予算を組んでいないのに、毎年100万円以上もお金出ていったら、思うように貯金ができないのも当然です。
・・・
そこで「毎月の生活費」と「貯金」とは別に、「特別支出」という予算をつくって、その分を確保することにしたのです。
そうすると「貯金」は、クルマやマイホーム、教育費、老後資金など、目的以外では取り崩さなくなります。
目標に向かって、着実に貯まっている感覚を持つことができます。目標との距離も明確なので計画も立てやすい。
一方「毎月の生活費」は、予算を決めてそのなかでやりくりするしくみが機能します。「毎月〇万円使って大丈夫」という安心感も生まれます。
まさに「特別支出」は家計のクッション役です。
「特別支出」を設定すると、逆に「毎月の生活費」がグンと減ります(やっていくとわかります)
「毎月の赤字をボーナスでカバーしている」というご家庭は多いと思います。でもこれは、「特別支出」的な支出を「毎月の生活費」から出していたことが原因だったのかもしれません。
【ステップ3】生活費口座&家計の財布をつくる
これまで「家計のお金は3つに分ける」というお話ししてきました。毎月のお給料やボーナスが出たら、この3つに配分するってことですね。
・貯金(貯金口座)
・毎月の生活費(生活費口座)
・特別支出(特別支出口座)
まず「貯金」を分け、次に「特別支出」を分け、最後に残ったのが「毎月の生活費」です。
この「毎月の生活費」の予算でやりくりできれば、必要なときに必要なお金が貯まり(貯金)、家具家電などたまにあるちょっと大きな支出にも対応できます(特別支出)
毎月の生活費は、銀行口座とお財布で管理
毎月の生活費には、住宅ローンや家賃、公共料金など銀行口座から引き落しする支出と、食費や日用品、レジャー費、お小遣いなど現金で払う支出があります。
そこで、銀行口座とお財布(現金)を使って管理します。
・生活費口座:家賃や公共料金など口座引き落とし
・家計の財布:食費や日用品、レジャーなど現金支出(封筒やオンライン決済も併用)
最終的にまとめるとこうなります↓
・貯金→貯金口座
・毎月の生活費→生活費口座&家計の財布
・特別支出→特別支出口座
※貯金口座は銀行、証券会社、保険会社など預け分けることもあるので、複数あっても構いません。
お給料が入ったら、銀行口座3つとお財布1つにお金を配分します(配分の方法は今後ご説明します)
そして、日頃は目的別にお金を出し入れします。
・スーパーで現金で買い物をしたら「家計の財布」から
・住宅ローンや公共料金の引き落としは「生活費口座」から
・テレビを買ったら「特別支出口座」から
特別支出的な支出は、実際には立て替えて、あとで清算するかたちにしても構いません。それほど件数の多くない支出ですからね。
銀行口座の選び方
生活費口座は、ぼくは近所の信用金庫さんの口座を使っています。ネットバンクが便利なのですが、公共料金に対応していない場合があるので(特に水道)。ただ、月に1回、振り込みをしたり入金しに行くだけなのでいいかなと。
特別支出口座は、ぼくはセブン銀行さんの口座を使っています。セブン銀行のATMなら毎日7~19時まで入出金無料です。ローソン銀行さんも同じような条件です(2025年2月筆者調べ)
貯金口座は、ネット銀行を使っています。住信SBIネット銀行とSBI証券という組み合わせです。住信SBIネット銀行はコンビニATMの入出金手数料が無料になる条件が緩いです(2025年2月筆者調べ)
日頃意識するのは家計の財布だけ
銀行口座が多いので面倒なようですが、日頃意識するのは「家計の財布」だけです(食費や日用品など現金支出を担当)
・住宅ローンや公共料金などは生活費口座から自動で引き落してくれます
・特別支出はたまにしかありません
・貯金は目的以外では原則引き出しません
「家計の財布」に毎月〇万円と決めた予算を入れて、お財布の残高を軽く意識しながら月末までやりくりすればいいわけです。
こうすることで、支出を記録して月末に集計するタイプの家計簿と違って、月の途中で現金が半分以上残っていれば「今月は順調だな」、半分以下なら「ちょっと飛ばしすぎだな」と残高をなんとなく意識しながら「やりくり」できます。
【補足】自分のお金と家計のお金はキッチリ分ける
家族のお小遣いは「家計の財布(現金)」の予算から出します。そのあとは、自分の財布で管理します。
自分のお金と家計のお金は分けるってことですね。
主婦の方に多いのですが、自分のお小遣いを設定していないケースをよく見かけます。家計のことを思ってのことでしょう。もしくは、そもそもこういう発想がなかったのかもしれません。
でも、自分のことにお金を使わないのは無理な話です。スイーツを買ったり、雑誌を買ったり、お友だちとランチに行ったり…
こうなると、家のお財布から「遠慮がちに」お金を出す感じになってしまいます。
であれば、パパや子どもと同じように、自分のお小遣いを設定して、気持ちよく自分のほしいもの、やりたいことにお金を使った方がいいと思います。
また、こうすることで家計の状況も把握できます。
なかには「遠慮がちに…」といいながら、記録してみたら結構な額を使ってた!ということもあります(笑)
人は予算を決めないとズルズルと使ってしまうものです。
・・・
自分のお財布を作ったら、銀行口座とクレジットカード、〇〇ペイなども自分用を作ります。
自分の欲しいものをネット通販で買うときは、自分のカードを使います。そして、その引き落しは自分の口座からします。
こうすると立て替えの手間が省けて簡単に明確に管理できます。
・・・
ここまでは「家計のお金は3つに分ける」というお話でした。次は、この3つに毎月いくらずつ予算を配分するか?お話していきます。ここが日々の暮らしの満足度を決めますよ↓
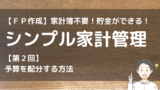
●ご質問・感想はこちらから。お名前・メールアドレス不要です。回答はこのブログで。
https://ws.formzu.net/dist/S17730087/
・・・
●メルマガ(無料)はこちら。シンプルに家計を管理する方法を最初から順番にお届けします。読むと気持ちが楽になるとご好評をいただいています↓
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=EvpylTAoA
●ご相談・お問い合わせなどサービスのご案内はこちら
https://fpushi.com/service